「完全2翻縛り」を中心に、ありありルールにも通じる三人麻雀が強くなるコツをお伝えします。
具体的にはあがりに特化した内容です。攻めを追求したい方、必見!
【三人麻雀】完全2翻縛りとありありルールとの違い
一般的にサンマは「牌効率」が重視されます。ツモられる確率が高いので、攻めが守りに直結しやすいからです。
ですが、完全2翻縛りのルールでは牌効率と並行して「手役の理解」が求められます。
2翻縛りを通じて、手役作りのコツを学ぶ
一般的なサンマは「立直」の1役で和了できます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
これが完全2翻縛りになると、自摸和了どころか「立直」すらかけられません。
理由はリーチの時点で2翻が確定していないからです。
では、2翻をどう作るべきか?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例えば、發を重ねて「立直、發」の2翻にするか。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
もしくは索子を落として「混一色」に向かうのがベター知れません。
もし、自摸った場合はどうするのか?
3pをツモってしまった場合、ルール上あがれません。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ
「混一色」に向かうのが楽そうですが、「メンツ手」も視野に据えます。
例えば西を対子にして、つぎに持ってきた数牌と發を切り替えて、くっ付きで「平和」を狙います。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
もしも、西を切った後で「發」が暗刻になれば、”フリテンリーチ”も想定します。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この辺りは1翻縛りのサンマとは異なり、回りくどく感じる点かも知れません。
2翻縛りの醍醐味は手役を考える力です。その構想力はあらゆる麻雀のルールに応用できます。
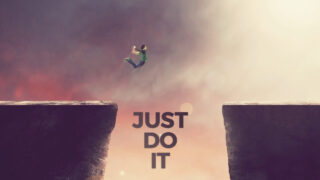
»【三人麻雀】完全2翻縛りルールで「勝ち続ける」方法【戦略編】
注意:完全2翻ルールでNGな打ち方
完全2翻ルールでは、早さが正義とは言い切れません。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この牌姿、ありありルールであれば無理強いな染め手は考えず、浮いた字牌を切り、手なりで赤赤を活かします。
ですが完全2翻ルールだと「混一色」がマスト。
理由は「發」が雀頭のメンツ手では「平和」が失われ、2翻が確定しません。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

これではNG。
完全2翻ルールでは、速度と手役をバランスよく理解する必要があります。
【三人麻雀】完全2翻縛りのあがり方を学ぶ
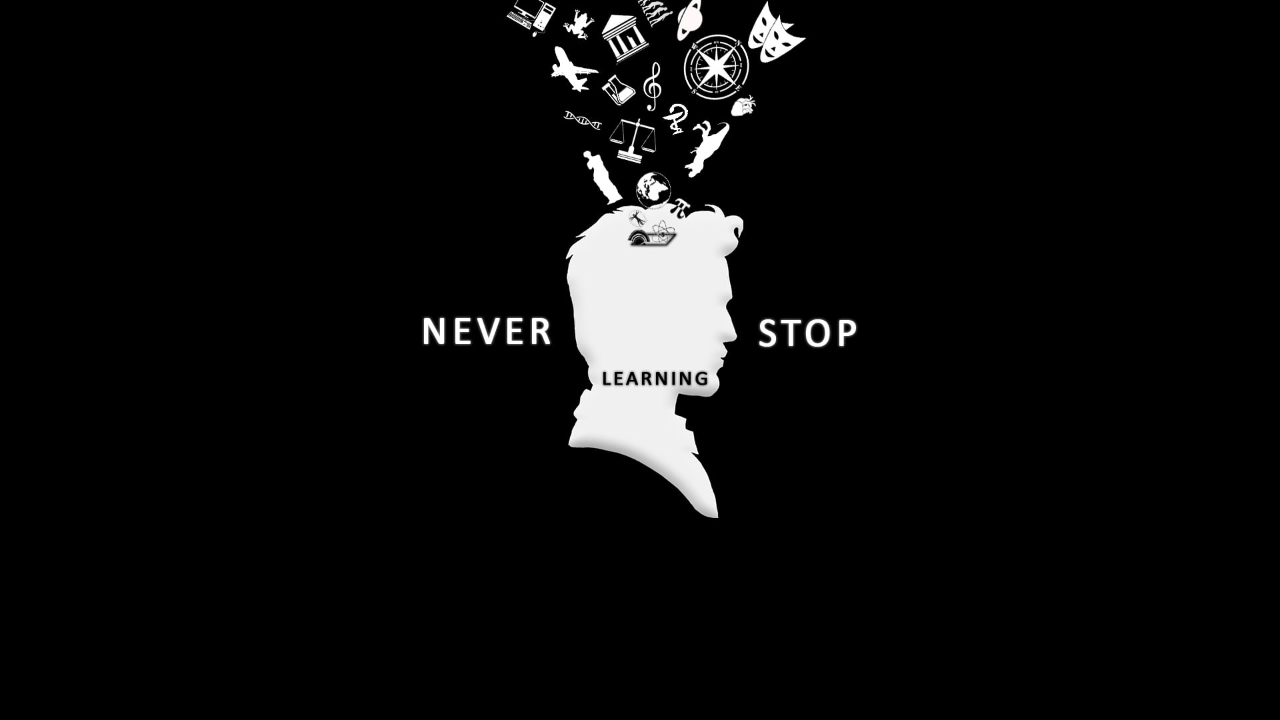
実力養成として、以下の配牌から最終形を考えてみてください。
すべて切り番です。
①:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
②:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
③:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
完全2翻縛りの「ルール」はこちら。

»【三人麻雀】完全2翻縛りルールと手組ポイントの解説【初心者編】
①:打ち進め方
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ぱっと見は「混一色」です。
筒子の縦重なりで「七対子」も据えて考えます。
形によっては「対々和」にもなりそうです。但し、状況次第では南を防御牌としても構えます。
例:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
②:打ち進め方
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
「混一色」を主軸に、4p重なりからの「一盃口」や「七対子」も視野に入れます。
ツモ次第では「断么九」への移行や、「中」が暗刻になれば攻防に余裕が生まれます。
サンマは基本は役牌1鳴きがセオリーですがこのルールでは、いきなり「中」を鳴くのはやや危ういかもしれません。(対戦相手や場況によりけり)
例:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
③:打ち進め方
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
まさに構想力が試される手牌。
門前で進めてリャンメン立直を打ちたいですが、最終系がカンチャンだと「平和」が付かず、白のトイツも気になります。
「混一色」に向かいつつ「メンツ手」に移行できそうなら、筒子の「一気通貫」など、ツモ毎に柔軟に構えます。
例:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

