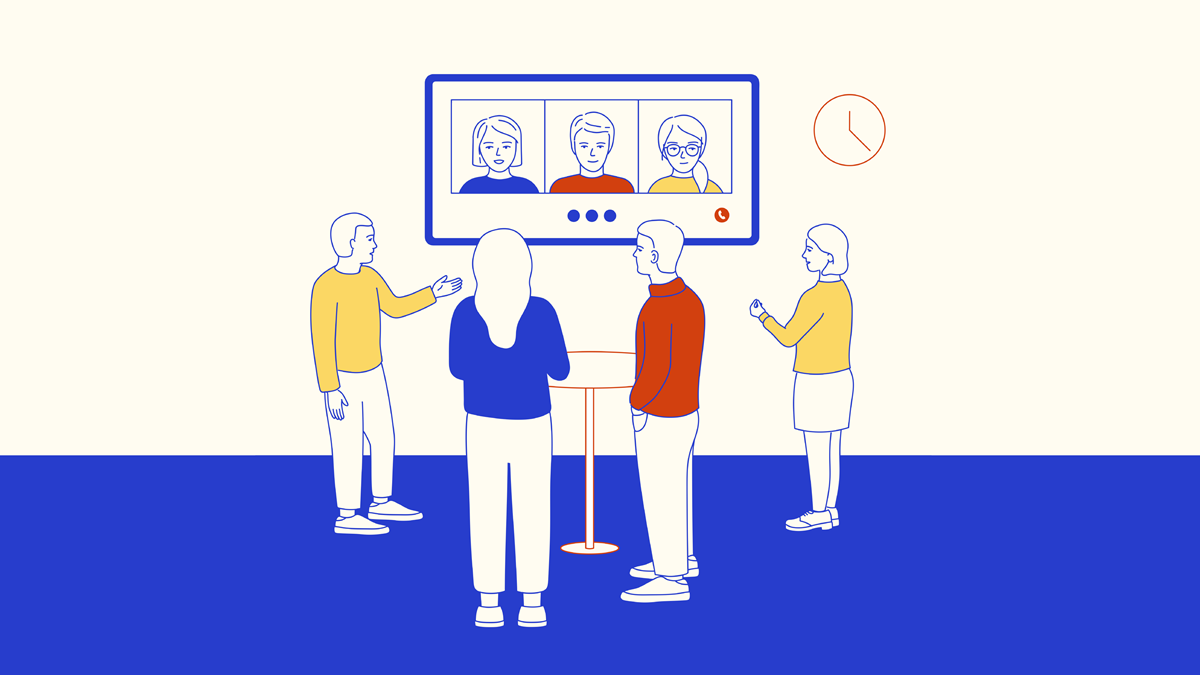リハビリ職にとって大切な役割の一つ、患者対応。
大切だと分かっていても、日々の業務に追われる中で、つい雑になってしまった経験はありませんか?
そんな「患者対応」のあり方について考えさせられる出来事があり、改めて真剣に向き合ってみました。
いつか自分たちも、患者や家族の立場になるかもしれないからこそ。
【患者対応】リハ職が忘れてはいけない尊厳と接し方【言語聴覚士】
40代になり、はじめて患者が身近に思えた
40歳代の言語聴覚士になってから、両親の身が少しずつ細くなってきました。そこで私はある発見をしたんです。

それは、病気です。
「ん?何言ってんの?」とおもいますよね(笑)
この病気とは、自分以外が経験する病気のことです。
赤の他人だからこそ、言ってしまった苦い経験
医療従事者は病気に対して冷静です。
言いかたは悪いですが患者は赤の他人だからです。赤の他人だからこそ、言えてしまうこともある…。
以前、私はある患者Faに「無理です、食べれません」と強いことばを言ってしまったことがあります。
嚥下障害は事実でも、大切なご家族が病気になった現実を直視できなかったはず。お辛い経験をさせてしまったと、猛省しています。
ある「介護士さん」の発言を耳にして
ベッドサイドでのリハ中、片麻痺の患者さんと介護士さんの会話が耳に入りました。
介護士さんが自分の子どもの悩みを話題にし、患者さんに意見を求めた瞬間、患者さんの表情が生き生きと変わりました。
私はその介護士さんを通じて、医療・介護職とは「世話」ではなく、尊厳なのだと深く気づかされました。

介護士さんのことも知ってほしい!
それと、SNSでときおり話題になる「患者への言葉つかい問題」ですが、いまならその本質が分かる気がします。
【患者対応】リハビリはサービス業なのか、単なる稼ぎなのか?

話はつづきます。
すこし繊細なテーマです。
私が一年目のころ、先輩から「リハビリ(医療)はサービス業だよ」と言われました。
実際、そのように考える医療従事者は少なくありません。 けれど、今の私ならこう答えます。

それは、違うと思います。
いきなり否定するようですが、きちんとした理由があります。
リハビリは「サービス業」ではない
サービス業の中心は”お客さん”です。
客を楽しませ、不快にさせないことがサービス業の本質です。
多少客側に非があっても、一旦は受け止めるのも仕事です。医療はあくまでサービス業的な要素を含んでいるのであって、本質そのものは全く違います。
医療者側が患者やその家族に必要に応じて「厳しく物を申す」こともあります。もしも医療がサービス業であれば、患者に物を申すだなんてあり得ません。
これは、サービス業経験者である私からの一意見です。
単位追求とホスピタリティのバランス
人としての優しさを持ちつつ、尊厳を意識して、ときには物を申すこともある。
そんな絶妙な距離感ではたらくのが私たちリハビリ職ではないでしょうか。
しかし近年ではこの構図が崩れてしまい、スタッフ自身がここを病むケースを見聞きします。

過剰なまでの”単位追求”です。
リハビリ職は「職場環境」あってこそ輝く
仕事である以上、稼ぎは大切です。だからといって過剰な労働(月平均21単位超えなど)は危険です。
そんな状態では、これまで述べてきた「患者対応」を真摯に行えるとは思えません。
はたらく(稼ぎ)とホスピタリティ。そのバランスが保たれる職場環境に身を置いてこそ、笑みのあるリハビリが為せるのではと思うのです( ̄ー ̄)ニヤリ

» 言語聴覚士は「リハビリが理解される職場」で働いた方がいい
ではー。