患者対応シリーズとして、今回はとても重要なおはなしをします。

カルテはきちんと書くこと!
カルテは大切な臨床記録であると同時に、リスク回避にも深く関わる土台です。つまり、STとしてのキャリアを築くうえでも重要な礎となります。
必ず目を通してください。

»【患者対応】リハ職が忘れてはいけない尊厳と接し方【言語聴覚士】
【患者対応】新人のうちに徹底したいこと【カルテはきちんと書け】
病室に監視カメラはない。
だから、自分たちの言動は自分たちで証明します。
先ず、下のカルテを見てください。
- O)昼食後のリハ。熱発後、看護師に報告。
- A/P)リハ評価、Do。
いくら何でもこれでは…。
何のための「SOAP」なのでしょう。
このカルテを見てヤバさを感じなければ、医療従事者として危険です。
もしも、この患者さんに”こと”が起きたとします。患者家族にカルテ開示を請求されたら、このSTの将来は危ういかも知れません。
明確なカルテを書く医師の話し(リスク回避にもなる)
わたしが敬愛する内科医(50代)のカルテは、文字が判別しやすく、5H1Wが明確でした。
以下はその一例です。
○月△日のVFにてペースト食は問題ないと判断し、〇月◎日の昼より□□STにペースト食の評価を指示した。
部屋持ちNr●●にはCFで報告済み。□□STには食事評価後のF.Bも依頼済み。経過次第では▲▲薬の経口を検討する。
分かりやすいカルテ(報告書)の多くは、”主語”がきちんと書かれているのです。
主語の欠落のせいで引き起こる「いった言わない」論争は日々のこと。記載不十分なカルテは多職種(特にナース)との間に軋轢を生みかねません。
STは「silent、NHCAP」などのある分野だけに、soapをベースに「5H1W」を意識した具体的なアウトプットを心がけてください。
» 無闇なポジティブアナウンスに注意|嚥下は「変化する病態」という認識
カルテの基本は、当たりまえなことを当たり前に記すことです。
【患者対応】具体的なカルテつくりの方法って?
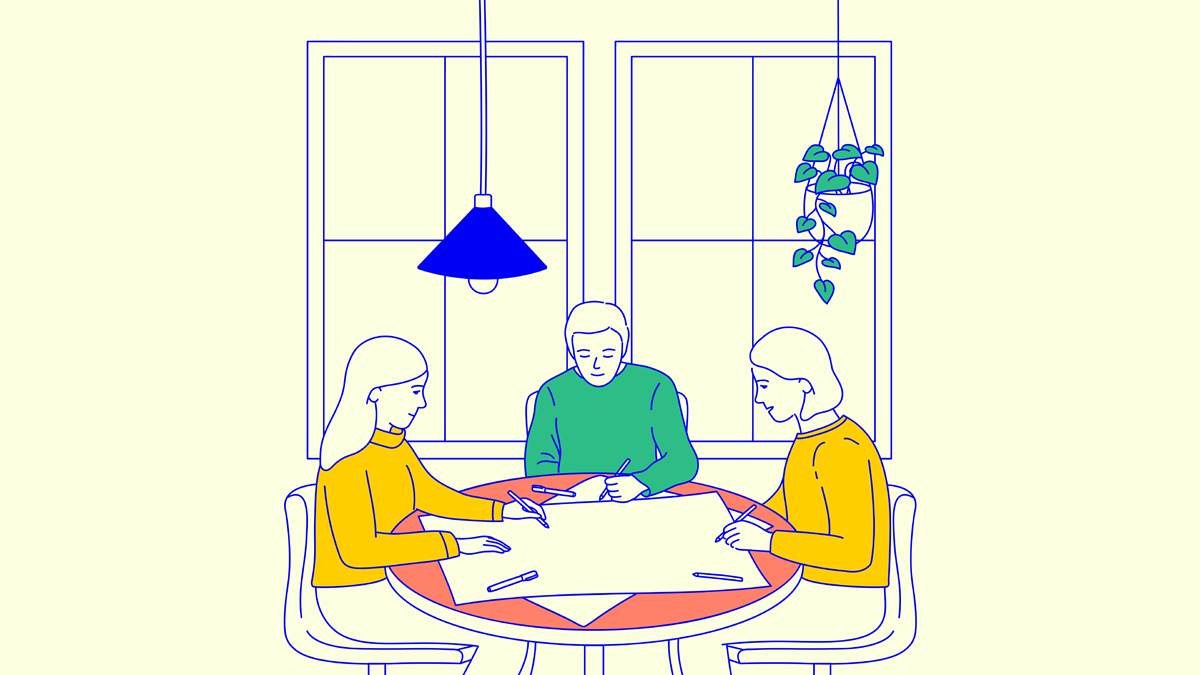
現在、執筆&工事中です。

こうご期待(汗)
カルテ記載には「オンライン学習」を活用する
カルテの学習はここだけでは足りません。
先輩からの指導や臨床経験も大切ですが、動画(オンライン)での学びは自分の弱点を手軽に克服できます。
オンライン学習で有名は『リハノメ』でしょう。
個人的には嚥下分野のカルテ記載で助けられました。学習成果は当然カルテにも繋がります。自由なタイミングで繰り返し指導を得られるのでおススメです。
実際に「医療訴訟」があることを知る
有名な「EARL先生」の発信。
減食で高齢入所者が衰弱、入院2週間後に死亡 施設を処分https://t.co/ewv0FfLJ45
「男性が食べられるのに減らした」わけではなく、「食べようとしなかった」ということのようですので、根本原因は別にありそうですね。市は「男性に対して摂食を促す努力を怠った」としていますが無理があるかも
— EARLの医学ノート (@EARL_med_tw) February 15, 2025
当然ですが、役所や家族は現場の実情を知りません。分かることといえば、現場との認識の差でしょう。
その差を埋めるのは、まぎれもなく私たち医療者の記録。そう、「カルテ」もそのひとつです。
一体、どんな事が医療訴訟になるのか?
以下の文献は医療訴訟のきっかけをまとめたものです。カルテ記載の参考にしてください。
» 誤嚥事故に関する医療訴訟の解析|日病総診誌 2020:16(5)
文献の要旨。
- 20年間で26の裁判例の解析
- アクシデントは「介護施設>病院」の順
- 誤嚥事故の容認率は57.5%
- ほぼ死亡事故、重度後遺症
- 1000万円以上の高額賠償
医療事故の予防に役立った内容は以下の通り。
- 見守りは適切であったか
- 食形態は適切であったか
- 誤嚥時の救急対応は適切だったか
- 経口、経腸栄養以外の選択肢
こういった現場の記録が、訴訟の予防や減少に役立ったと伝えられています。

詳細は文献のURLをご覧ください。
自分を守るため、組織を守るため、そして患者を守るためにできること。そのひとつがカルテであることを忘れないで下さい。
ではー。

