カニューレ患者さんへの「離脱に向けたリハ」の症例報告です。
いま現在、カニューレ患者さんへの対応をしており、離脱への検討をされているSTや看護師さんのご参考になれば幸いです。

さいごに「必読書」を紹介しています!
【症例報告】カニューレ患者への初回評価と確認
結論として、私の経験したカニューレ患者さんは「初回介入から2か月ほどで離脱」に到達したかたでした。

VF・VEの無い病院での対応になります。
初回印象と評価
- 心原性失神からの「単管カニューレ」対応
- 下肢性閉塞性動脈硬化症
- 意識清明、血圧変動あり、やせ型
- コミュニケーション能良好(筆談で可)
- 中間とろみ、ペースト食(3食ベッドサイド)
- DSS4~5、藤島7&7
- ADL概ね介助(車いす移乗など)
- 吸引孔からの痰は中量
筆者の拙い経験ではありますが、評価上、スピーチカニューレへの移行はできそうだなと判断。
”経験上の話し”ですが、コミュニケーション能は患者の予後を示す指標だと考えています。
1:リハの前に確認すべきこと
当然ですが、STだけでは対応できません。
自分の働いている病棟のマンパワーの確認は必須です。
- 耳鼻科医師がいるか
- リハ医がいるか
- 病棟の理解力・協力性はどうか
- 「高位気管切開」かどうか
これらの確認は患者への対応に関わってきます。例えば、良好と思われたカニューレ患者でも、場合によっては次第では窒息するケースがあります。

リンク先の話しでは、肉芽形成による下気道閉塞だったようですが、耳鼻科医による素早い対応が行われています。
ほかにも、寝たきりによる虚弱からの「NHCAP(医療介護関連肺炎)」でしょうか。人員介入が疎かになりやすいケースでは注意が必要です。
2:「見えない部分」の確認で重要なこと
- 呼吸器合併症(既往)の確認
- 気管切開になった理由
- VF・VEがあるか
既往歴は言うまでもなく、必須なのは、気管切開になった理由の把握です。
カニューレ対応のケースでは心臓や肺に疾患があり、心臓オペによる「反回神経の損傷」や「気管挿管による声帯損傷」などがあります。そこで想定されるリスクは「声帯麻痺」です。
もし声帯が麻痺や損傷によって正中位に固定されている場合、痰が声帯に絡むことで窒息の危険性があります。
それを知らずに「カニューレ離脱」をすればアウト。ひとつの例に過ぎませんが、VF・VEの無い病院では慎重さを求められます。

»【頸部聴診法】VFのない病院での嚥下評価でSTが意識していること

事前の確認を怠らずに!
【症例報告】カニューレ離脱に必要な条件【中間評価】

自身の経験と医療的な手順を、おおまかに記します。
カニューレ離脱および、スピーチカニューレへの条件
学研の専門書によると、全身状態の安定、酸素化不要、JCSⅠ桁、離床が可能の4点が挙げられています。
そのほかの詳細も書いておきます。
バイタル・呼吸機能の安定
- 自発呼吸を安定して行えるか
- 酸素飽和度が適切な範囲にあるか
- 咳嗽力は保たれているか
- (内筒を外し)気管孔を塞いでも呼吸は楽か
気道・口腔のクリアランス
- 肺炎兆候がないか
- 吸引する痰の量が少ないか
- カフ脱気後、昼夜通して問題ないか
- 口腔内は清潔かどうか
身体・嚥下機能
- 「下肢筋力」は保たれているか
- 座位の姿勢は取れるか
- 経口摂取の前後で変化はないか
- 自力摂取できるか
今回の症例さんでは、これらの項目をチェックして、スピーチカニューレへ移行しました。
【症例報告】スピーチカニューレ後のリハビリと対応
入院から概ね3週間程度で「スピーチカニューレ」に移行しました。
スピーチカニューレ後の「リハビリ」
- 吸引で痰量確認
- ベッドサイドでの呼吸リハ
- スピーチバルブにて発声ex
- 車いす移乗、呼吸、発声
- トロミ水、ゼリー、固形物
トロミ水2~5mlを随意 → 自由嚥下、フードテストと段階を上げて、着色水で気道分泌物の確認も行いました。

カフ圧はクリアリング次第で脱気。
呼吸・発声訓練の詳細
| 対応 | 訓練内容 |
| 胸郭の徒手的なアシスト | 深呼吸の促し |
| 吸気時はカニューレ孔を解放 | 呼気時に孔を塞ぐ |
| ベッド座位での訓練 | 咳嗽訓練 |
| スピーチバルブでの訓練 | 孔を塞ぎ、発声 |
| 発声訓練 | 「母音→破裂→摩擦・弾音」へ誘導 |
スピーチカニューレ後の「対応」
3日後には日中帯、そして1wで24時間カフ脱気での生活を病棟に申し送りました。
嚥下は「軟飯、軟菜」を3食自力、ベッドサイドおよび昼は食堂で対応。
その状態で酸素化をはじめとした、諸々の問題が生じなければ「ウイニング(離脱)」だと考えました。
病棟との連携が欠かせない
諸々の問題の一つが「肉芽形成」ですが、今回の症例さんでは生じませんでした。意外と注意なのは、患者さんが動けるようになった後です。
怪しい色の痰や、血色痰などは直ちに、医師・病棟に連絡です。
それと、スピーチカニューレ後に嗄声(湿声も)が続くようなら注意です。声帯の状態によっては「声帯麻痺+痰」による下気道閉塞のリスクがあります。
【症例報告】カニューレ離脱直前、直後の状態【最終評価】

最終評価
入院後3週間でスピーチカニューレ → そこから約2週間後に「離脱」しました。
- 食事は3食車いすで自力摂取
- 軟飯・軟菜(年齢考慮)
- トロミなし
- G1.5 R1.5 B1 A1 S0
車いす自走、トイレは見守りなど、ADLは一部改善。
その後の対応
離脱後は数回程度、再評価を行いSTは終了。PTに後方をお任せし、身体機能の向上に努めてもらいました。
カニューレ離脱後、しばらくして「閉塞性動脈硬化症」の悪化がありましたが、ST領域への問題は生じませんでした。
この患者さんとの感想や思い出はこちらで語っています。
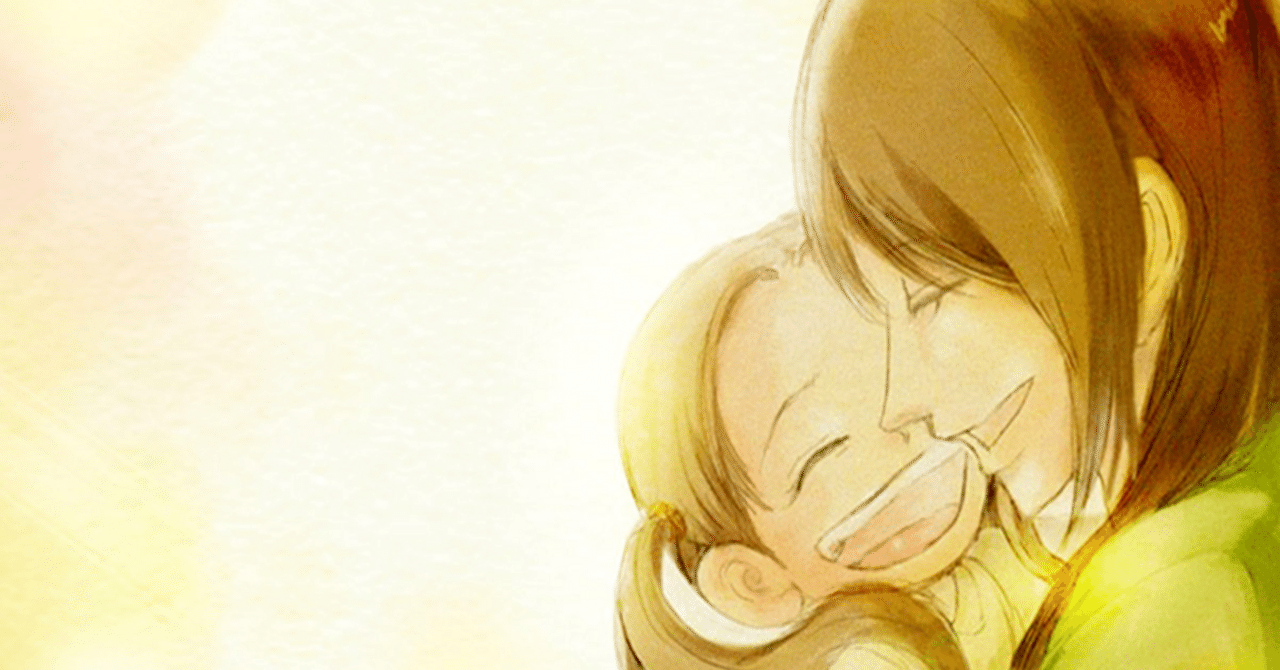
【参考書】カニューレ患者対応に持っておきたい必読書
2冊ご紹介します。
今回の症例にも役立たせて頂いた、最高の2冊です。
カニューレ対応前に必ず目を通しています。STでも、看護レベルの本を1冊は所持したいところ。
「WEB動画」で嚥下を学べる1冊。テキストだけじゃ深まり難い分野なので動画があるととても助けられます。
ではー。

