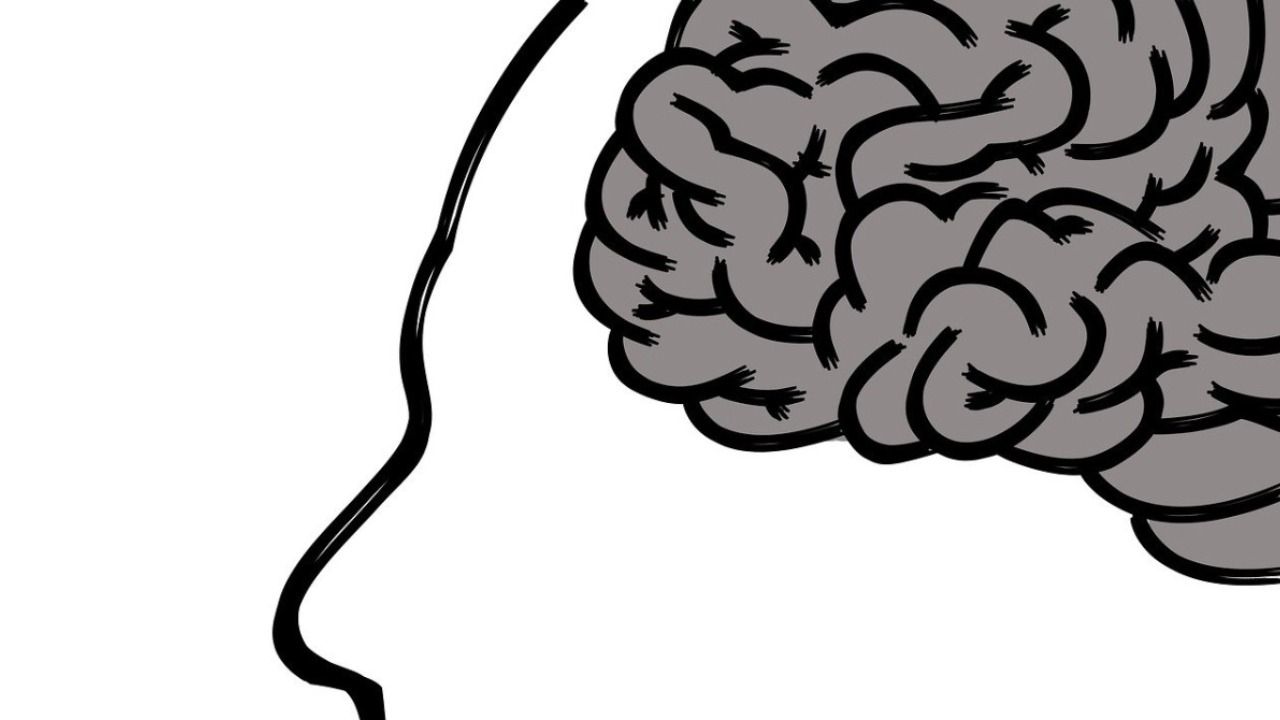こんにちは。
脳画像を見るのが好きなかづおです。
STにとって必須といえる脳画像の知識。
でも「すこし難しい…」とおもう方もいると思います。
ここでは私が実際に読んで『わかりやすかった』&『読影力が高まった』と実感できた2冊の参考書をご紹介します。

おススメの2冊です!
【読影力】脳画像の新しい勉強法を学べるおススメの参考書をご紹介
ご紹介する2冊はこちら。
2冊とも『リハ向け』に書かれた参考書です。
先ずはシンプルに解説している「①」からご紹介します。
その1:脳画像の見方と神経所見

まずこの参考書を買いましょう!
もうね、ほんとうに分かりやすいんですよ。
脳血管を扱うSTであれば、よく目にする疾患を少ないページ数で「コンパクト」に学ぶことができます。
読んでいて分かりやすいと感じたのは『損傷部位と病名』~『起こる症状』をしっかりと対応させて掲載しているあたりです。
おなじ被殻出血でも、血腫量の違いに応じた掲載をしているので、症状の違いが分かります。
また損傷部位の詳細を「図式」でも解説しているので、画像初心者でもイメージが付きやすいです。
その2:脳画像の新しい勉強本
フルカラーでお値段4,000円台。
タイトルの通り、新しい知見が満載のすばらしい参考書です。
私的見解ですが、ここまで『言語聴覚士より』な脳画像に出会ったことはありません。
「読影力の向上」を求めているSTであれば手に取ってほしい参考書です。
STに特化した「読影力」が身に付く参考書
すばらしい脳画像参考書には2つのポイントがあるかと考えます。
- 病態と画像をリンクさせているか?
- 分野別の解説があるか?
まず本書の特徴は『2D・3D画像』を駆使して神経ネットワークを学習できます。
PDの解説ページがあるのですが、中脳上丘から下丘までの黒質変性を、T1とSWIに別けて神経症状を説明しているあたりなんかは、筆者の「高度な読影力」がうかがえます。

もう一点は「分野別の解説」です。
この本を読んで驚いたのは『失語・高次脳の解説』が具体的(STより)であること。
喚語困難や錯語、それに嚥下障害などの症状を「どのネットワークの損傷で生じるのか?」という点まで掘り下げています。
単なる読影ではなく「症状」までをも網羅的に記されているため、より深い読影力を得ることができます。
読影力が身に付くとわかること【予後予測】
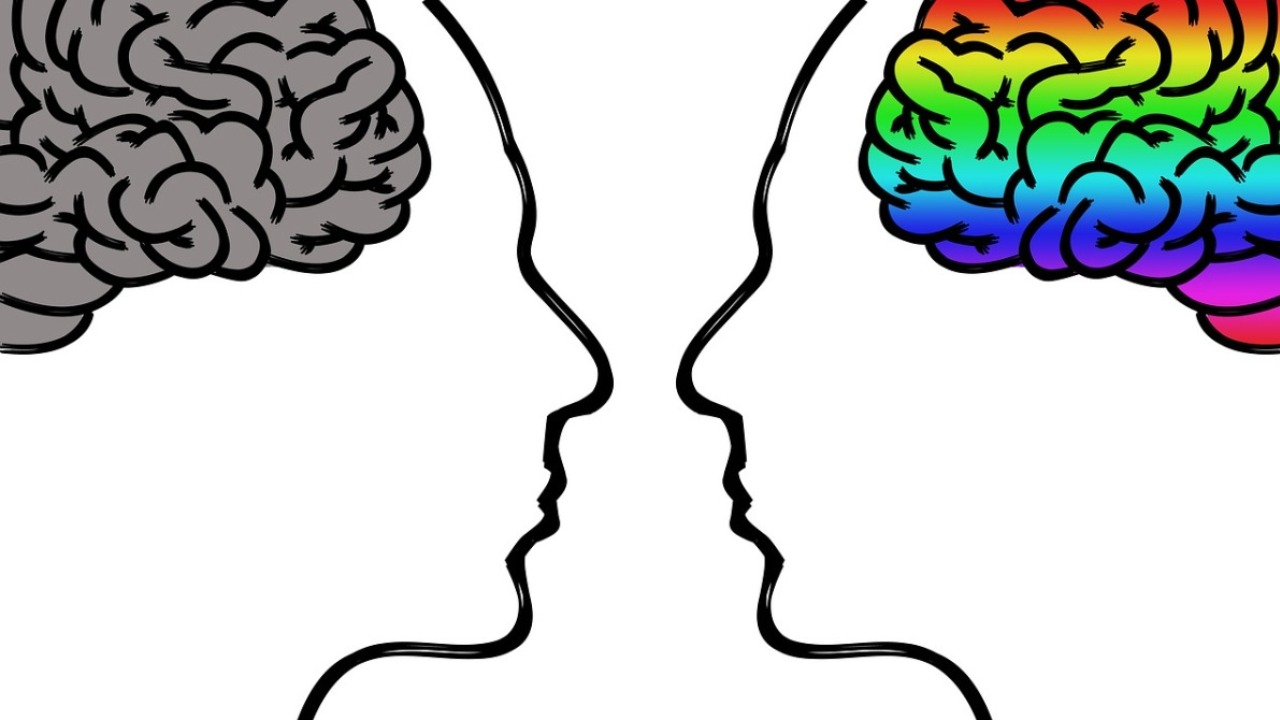
高次脳は複雑で難解な分野ですが、少なくとも脳がわかれば『予後』を知る手掛かりになります。
というのも、画像評価をしていくと「古い病変」が見えることがあります。
例えばそれが嚥下に関わる領域(島回など)に散在していた場合、いまは落ち着いているようにみえて、じつは「水分誤嚥」の進行なんかがあるかも知れません。

島回は水嚥下で賦活するためです。
また、現病は小さいのに認知症状が出ている場合、もしかしたら再発を繰り返した陳旧性病変の影響なんかも考えます。
病気の『量』は現場で評価できますが、脳画像にて『質』を知ることで、患者さんの予後予測の見立てになるかもしれません。
さいごにリンクを貼っておきます。
ではー。