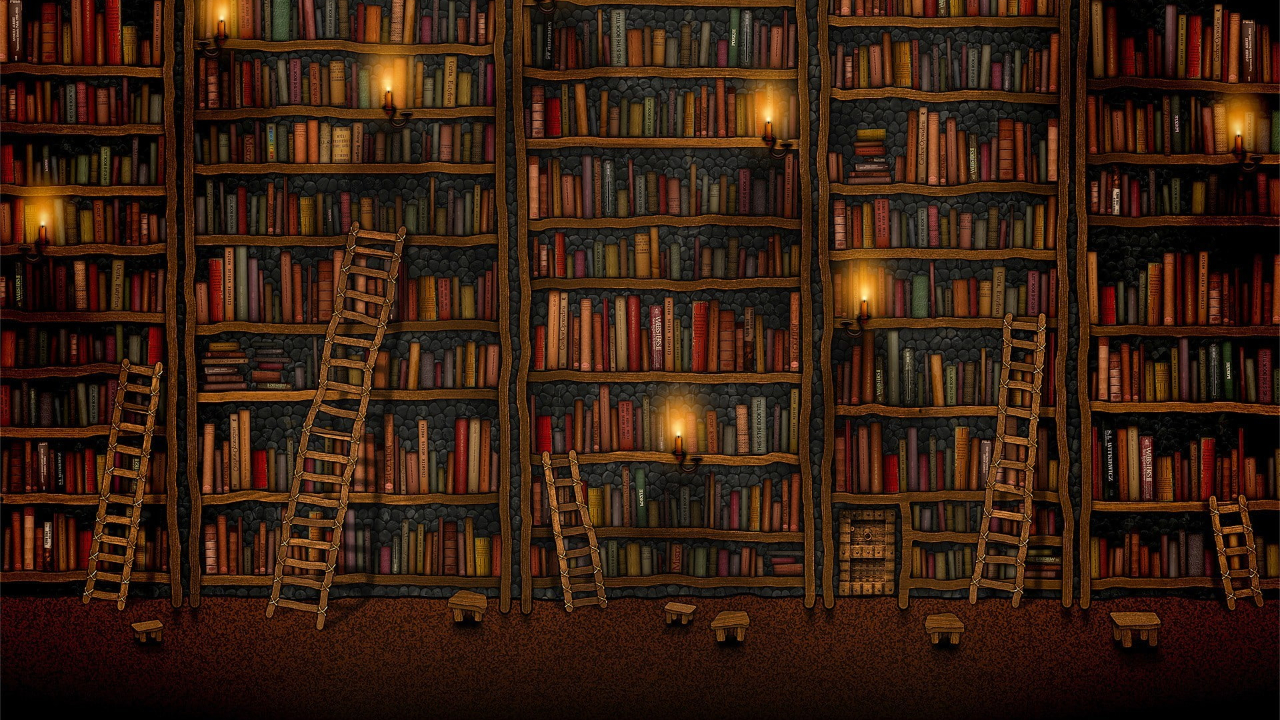言語聴覚士のかづおです。
新人のころ、先輩方に勉強の質問をするとたくさんの本をすすめられました。

でも、STの参考書って何が良いのかな?
たくさんあって迷いませんか?
ここでは私がいまでも臨床で助けられている、基礎ベースの本を『分野別に』ご紹介します。領域は成人分野です。
どの本を買えばいいか分からない方は参考にしてください。
【厳選】成人領域の言語聴覚士におススメな参考書【基礎ベース】
以下の領域に対応する本を、厳選してご紹介します。
- 失語症
- 高次脳機能障害
- 嚥下障害
- ディサースリア
- 脳画像
失語症
失語はこの2冊が臨床をフォローしてくれます。
2冊とも良本ですが、個人的には「失語症臨床ガイド」の『症状別のアプローチ法』が、役立ちました。
「感覚失語への意味を利用した単音節訓練」
「純粋失読への視覚系を対象にした基礎訓練」
このような各タイトルが用意され、患者さんへの訓練を『ポイント別に深堀』して、紹介しています。
発売日は古いですが「訓練プログラムの辞書」として、いまでも臨床に役立ちます。
高次脳機能障害
高次脳臨床で大変お世話になっている2冊です。
高次脳の基礎解説と一緒に、課題シートも掲載されており「付録のDVDで印刷」することができます。
2冊とも、各症状別の基礎から『就労支援のレベル』にまで、学びを深められます。
嚥下障害
嚥下の臨床には必須といえる2冊。
著者「藤島先生」を含む、有名本です。
観察すべきポイント、頸部聴診のトレーニング、嚥下障害への対応法を「挿絵付き」で解説。初学者にはもってこいの参考書です。
付録のDVDで『VF、VEも学べる』ので、座学で読影力を身に付けられる、ベストな2冊です。
運動性構音障害
この2冊を通じて『徒手的なアプローチ』の必要性が理解できます。
「アライメント」や「筋トーン」の調整といった、神経・筋促通によるディサースリアの治療法が解説されています。
机上だけの構音訓練はこれで卒業です。
構音だけでなく『嚥下・呼吸にも応用』できます。
脳画像
脳画像の知識を、この一冊でアップデートしちゃえます。
この本、ホント分かりやすくておススメです。
脳画像の種類や特徴から始まり、障害部位による神経症状など、画像付きでとても分かりやすく紹介しています。
「百聞は一見に如かず」を表した参考書でして、脳だけでなく『血管病変の解説』も含みます。
「おまけ」ポケットマニュアル
「ポケットマニュアル」シリーズから1冊だけご紹介します。
このシリーズ最大の利点は『携帯性』です。

MWSTの3aって…。
こんな瞬間ってありませんか!?
わたしは評価点のアンチョコとして使ったりします。
ですが、この本のみですべてを網羅するのは不十分でして、やはり各種専門書に目を通す必要はあります。
ケーシーのポケット内にあると安心できますよ~。
【臨床特化】専門性の高い参考書「まとめ」はこちら
続いては、より『専門性の高い』参考書をご紹介します。
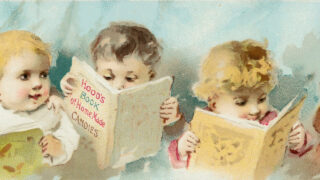
»【厳選5冊】言語聴覚士が持っておきたい参考書まとめ【臨床ベース】
こちらは基礎も学べつつ、臨床力をUPできる本のまとめになっています。気になるSTはぜひ一読ください。
ではー。