こんにちは。
万年ヒラSTのかづおです。
新人だったあの頃、まさか自分が「後輩さんをもつ立場」になるとは思いませんでした。

新人教育…どうすればいいんだろう。
このブログでは、私が培ってきた『育成方法』とその『記録』をお伝えしていきます。
ボリュームのある充実した内容ですので、期待してお読みください。
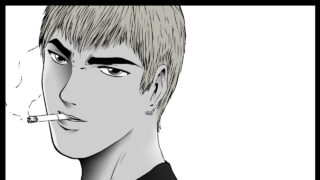
»【言語聴覚士】バイザーが「意識」しておきたい実習生との接し方
新人教育に悩む言語聴覚士に知ってほしいこと【コーチングのすゝめ】
さきに私自身の話しをさせてください。
これまで教育に触れる機会がなかった私は指導が不安でした。
- ちゃんと教えられるかな…
- ことば使いは大丈夫かな…
- ミスをフォローできるかな…
いまおもえば『自分中心の不安』ばかり。
一番不安を感じているのは後輩さんだというのに。
にも関わらず、口ばかりは達者で、指導を通じて先輩らしさをアピールしようとしていました。

自分に「自信」がなかったのです。
ですが、虚勢を張る先輩なんてのはただの強がり。
当時のわたしは、後輩を受け入れようとする姿勢にとぼしく、自己中心的で『誘導的』な指導ばかりでした。
そんな傲慢な私に「指導の本質」を気づかせてくれた本がありました。
指導者に必要な「コーチング」とは?
その本とはこちら。
数々の指導本を読みましたが、こちらは最高の一冊といえる本です。
この本では指導を「コーチング」と呼び、これは『聴く技術』だと説明します。
コーチングとは、会話によって相手の優れた能力を引き出しながら、前進をサポートし、自発的に行動することを促す「コミュニケーションスキル」です。
コーチングとは、聴く姿勢をもつことで相手に考えさせ『自己成長の機会を与える』といった指導法です。
過去の私はそもそも『聴くってどういうこと?』という状態だったのです。
コーチングとは相手を「受け入れる」技術である
結論をいいます。
「聴く」それは、相手を受け入れる(承認する&肯定する)ということです。
コミュニケーションは話すことよりも、むしろ「聴くこと(受け入れること)」のほうが重要である場合が多いのです。
つづいて重要なことを説明しています。
聴いてくれる相手がいる環境は『安心できる場』であり、安心感はその人により深い洞察力を与えます。

とても重要なことですね。
前提として「ここは危険だ」とおもえる場所でひとは成長しません。高圧的な上司や先輩なんかはそれに当たるのでは?
過去の私のように「誘導的な指導」をして、聞く耳をもたない様では、成長どころか人間関係にヒビが生じます。
ひとの成長とは、相手の意見を否定せず、まずは『聴き、受け入れる機会を作る』ことで促されるのです。
指導ってシンプルで『相手中心』なんです。
(コラム)なぜ、指導者が聴き入れる「機会」をつくるべきあなのか?
さて、「新人が学ぼうとしない」という指導者の声がまれにあります。
指導者の目線ではそう見えるのでしょうが…。

何故そう見えるのでしょうか?
教育は一朝一夕ではおこなわれません。
人の成長は「緩やかなチカラでゆっくりと時間をかけ続ける」ことで、開花します。
指導とはある意味「種まき」なので、肥沃な土であればより成長しやすいわけです。そしてその土とはまさに『環境』を指します。
そして、その環境を整えられるのは、組織の構造上『上役の役目』なのです。
もし、後輩が育たないと感じられるのであれば、いま一度、ご自身の立場を見直してみてください。
職場の「教育環境」はどうですか?
コミュニケーションを「促進」させる聴き方

ここから実践編です。
「聴く」といわれても実際にどうするべきなのか?
コーチングの本では、3つのステップだと述べています。
- 聴いて
- 受け入れて
- 質問する
ポイントとしては、相手が話しているときに「あーそういうことね」と自己解釈しないこと。

すでに誘導気味で、話を聴いていません!
相手が話し終わったら「こう言い返そう」とか考えがちじゃないですか?
大原則として『相手が話し終えるまで、黙ったまま』でいましょう。性急なアドバイスはかえって「否定」をうみます。
ただし、明らかな間違いを述べるようなら、こちらから話を挟むことはあります。そのときは「それもありそうだね」などと『ワンクッション挟んでから』自らの意見を伝えます。
肯定すると、相手の「価値観」に気づける
基本的には聴き入れ、相手の意見を『肯定』するよう徹する。
こちらが聞きたい内容をばかりを求めていると、重要度の尺度を見誤ります。アナタにとっては重要ではなくても、後輩にとっては成長のチャンスだったりするからです。
こういった姿勢に徹ってしていくことで、相手の『価値観』に気づけるようになったりします。
「価値観」とは成長のツボである
相手の話しを聴いていくと、キーワードとも取れる「価値観」が話されるときがあります。
ここでいう「価値観」とは、各々の信念に関わってくる重要な部分です。したがって、この価値観が現れたというのは、成長の可能性が浮上してきたともいえます。

成長の「ツボ」ですね。
そんな重要なタイミングで、話し中の相手に「こう言い返そう」なんて考えていると、相手の価値観ワードを聞き逃しかねません。
価値観を引き出すという意味でも、指導者は、聴き手役に徹するメリットがあるのです。
ここからすこし私の経験談をお話しします。
「質問」から変化した後輩のおはなし
私の後輩でAさんというSTがいました。
Aさんは新人症例発表会の日程が近いにも関わらず、その準備を一向にしようとしません。
Aさんはよく「勉強が分からない」「わたしにはできない」というネガティブな発言を頻繁にする子でした。
ですが、ことばとは裏腹に、患者さんへの対応は真剣そのもの。私はそんなAさんの発言に『違和感』を感じていました。
その違和感とはAさんの持つ、高い目標です。
答えはその人のなかにある
私はF.Bの時間をつかい、Aさんとコミュニケーションを図りました。
Aさんはどうやら「できない」のではなく、目標に到達できない自分自身に、諦めのような心情を抱いていたようです。
自分=できない、そんな恥を晒しかねない症例発表会に不安を抱き、前進できずにいる…といった状態でした。
*
私はしばらく話を聴いたあと、「その目標を持った理由は?」という質問をしました。
しばらく沈黙が続き、Aさんは自身の”複雑な生い立ち”を話してくれたのです。
私ははなしを聴いたあと「その高い目標はAさんの長所だね」と伝えました。
するとAさんは「え?」という表情のあと、しばらく沈黙が続き、ちいさく頷いたあと、普段の雑談にもどりました。
その日を境にAさんの進撃がスタート。
結果、堂々たる発表にいたりました。
*
発表会の帰り道、Aさんが放った一言はいまでも忘れません。
わたし、前に進めた、進んでます。
私のなかではAさんに対し、際立ったアドバイスなどはしていません。
『聴き、質問をしてみた』だけです。
また、この出来事が必ずしもコーチングの成果かどうかはわかりません。
とはいえ、Aさんが前進するキッカケになったのでは?、そう考えています。
おわりに
ここまでお疲れさまでした。
聴くに慣れたSTといえど、コーチングを知る機会はあまりないのでは?と思います。
これを機に学んでみてはいかがでしょうか?
ではー。

